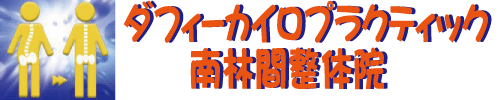今まで特にスポーツの現場などでは、体幹を鍛えるというと体幹部を固めることにより強度を増し、負荷に耐える。そして動きは股関節の分離運動で行う、みたいな方法論が傾向としてあったように思います。これはバイオメカニクス的側面から腰痛を研究しているStuart McGillをベースとした方法論ですね。
Stuart McGill ナップ 2017-05-30
ですが最近の流れとしては、体幹部も適度な強度を保ちつつも、柔軟に動いていけるようにする、というような体幹部のコントロールの質的な変化を求められるようになってきていると思われます。その指標の一つとして腹横筋の分離運動ができるかどうかがあるようです。
今回の講義では、なぜ腹横筋の分離運動の獲得が必要かを理解する事ができたのが収穫の一つでした。
講義2日目
2日目は1日目の講義の内容の実技編です。
主に体幹筋の評価に時間が割かれました。筋の評価はかなり細かく行われました。
ふむふむ、やっぱり、こんぐらい細かくやらないとダメなんだよね~、など認識を新たにさせられました。
そこで実際使わせてもらって、コレ、絶対ほしい!!と思ったのが「超音波診断装置」です。
参加者の大半が理学療法士だったようで、半数くらいの方がすでに使用した事があったようですが、私は使うのが初めてでした。
これを使うことによってクライアント様に腹横筋の使う訓練の大きな補助となります。運動感覚だけにたよると、普段その筋を意識的に使うことができる人であれば、運動感覚を得ることは造作もない事です。しかし、今までその筋を意識的に使ったことがない人には運動感覚を得ることは困難を伴うことが多くあります。自分の筋が動かしているところをリアルタイムで画像から情報を得ることは、運動感覚を理解するために大きな助けになります。
画像診断装置なので、画像から骨折などの「診断」ができてしまいますが、『診断」行為は違法などで診断はしません。しかし、筋の状態の「観察」は行っても問題ありません。超音波画像診断装置は薬事法上ではクラスⅡで、電子血圧計や電子体温計と同じ扱いになっているので、使用しても問題ないと思うのです(まだ、詳しく調べてないので、正確なことは言えませんが)。
しかし、腹部のトレーニングだけにコレを買うとなるとコストが半端ない。う~ん、でもほしい。
どなたか、もう使わないから譲ってやるよ!って方いませんか(できればポータブルで)?
感想とまとめ
腰痛の原因には多岐にわたっており、今回の腰痛アプローチのターゲットは侵害受容性の腰痛(簡単に言うと動くと痛い腰痛) がメインだったので腰痛全てを網羅したものではなかったのですが、それでも我々ができる事や、すべき事はまだまだ多くあるな~という感想を持ちました。
またこの様な研究ベースの知識と、今まで自分が学んできた事や臨床から得た方法や技術が結びつくことにより、ブラッシュ・アップされたり、より自信をもってクライアント様に提供できるなるという意味で有益なものでした。
今後ともクライアント様にさらに貢献できるよう、研鑽を積んでいきたいと思います。では、今回はこの辺で。