腰痛からバーベルスクワットへの復帰と予防について
【今回の記事はブログ統合のため、他ブログより転載したものです(初出2015年12月)。】
今日は、今回は前回に引き続き、バーベル・スクワットと腰痛との記事の実践編です。
当院では、まず腰痛の回復のための機能トレーニングとして、腰部多裂筋&腹横筋の共同収縮がキチンとできるように練習していただきます。それができるようになってから次の段階として、以下のさらに負荷をかけて本格的な運動をする前段階のエクササイズを推奨しています。今回のご紹介はこの辺りからのお話しです。
モデル:パルンボ井若
1、体幹部の固定の仕方
ここで注意しておきたいのは、一般にコアトレとよばれている体幹筋のエクササイズは、ドローインとよばれているお腹を引っ込めるような収縮を練習させられますが、アレは深部筋の腹横筋をなるべく単独収縮させるのを狙って行われます。
深部筋は、体の動き始めの最初の部分で、脊柱を安定させるために働きますが、筋の出力自体は弱く、それだけでは重量物は支えられません。重い物を支えるための体幹筋の使い方は、ブレージングというお腹を気張らせる収縮の仕方を使います。
これは、意識しなくても重い物を持とうとすれば、自然とそうなります。日常的にも排便の時に腹圧を高めるために無意識で使っています。したがって、スクワットをする時も当然、使うのはブレージングです。不自然にお腹を引っ込めるような動きをしないようにしましょう。
2、スクワット復帰&腰痛予防のための種目
2-1、リバース・ハイパー・エクステンション
起立筋のエクササイズというとバック・エクステンションやグットモーニング、ベントオーバーなどいずれも脚部を固定して上体を動かす種目が多いですが、リバース・ハイパー・エクステンションは逆に上体を固定して下肢を動かす動作になります。これが特に下部腰部・骨盤部の深部筋(多裂筋)と表在筋との筋連鎖と協働収縮の感覚を掴むのに役立ちます。
リバース・ハイパー・エクステンションの参考図はNSCAのページをご覧ください↓
図ではバランスボールを使って腰を上げていますが、トレーニングベンチやイスなど上体が固定できるものがあれば何でも構いません。膝と股関節が曲がった状態から、膝と股関節を伸ばしながら下肢を持ち上げます。図では下肢は大きく上に持ち上げていますが、腰が痛い人は持ち上げる高さは腰の高さまででです。それを越えると腰が反ってしまい、腰を痛めてしまいます。
2-2、レッグ・プレス&レッグ・カール
スクワットができない時期の脚部の代替メニューとして、真っ先に上がるのがこの2種目です。クローズ・キネティック・チェーンであるスクワットに対し、オープン・キネティック・チェーンの種目になるので、運動様式が違ますが、腰部に負担をかけずに大腿を鍛えられるので、スクワット復帰まで脚の筋力を保のに必要かと思われます。
2-3、パーシャル・スロー・スクワット
スクワット時に腰に痛みが出やすいとされる角度に、ボトムからの切り返しからスティッキング・ポイントまでの間が挙げられます(ここではフル~パラレルを対象とした話)。
筋肉は、痛みを慢性的に感じていると神経的に抑制が働き、筋出力が落ちてきてしまいます。特にしゃがみ込む場面で、ボトムに近づくにつれ腰部の負荷が増してくるところと、そこから重みを受け切り返して、重量を押し上げる場面がキツイ部分で、慢性的な痛みから抑制がかかる習慣が出来上がってしまうと、その部分がなかなか改善されません。
そのため、下部腰部の筋出力を発揮できるような再教育を行っていかなければなりません。先ずは、痛みが出るようなら重量が重過ぎるので、ウェイトを減らして行います。
パーシャル・スクワットで、先ほど述べたボトム近くの痛みが出る範囲の手前までのスクワットで慣らし運転をしていきます。通常、ウエイト・トレーニングでは効果を最大限に発揮するためには、フル・レンジ(可動域いっぱい)に動かす事が推奨されています。パーシャルとは、フル・レンジまで動かさないやり方のことを言います。スクワットではクウォーターやパラレルの手前(人によってはハーフという)までの可動範囲で行うことを指します。
その際、下降・挙上ともにスロー・スピードで動かすことを心がけてください。スピードが速いとチーティング(反動づけ)になりやすく、負荷が増大します。また筋の力も抜けやすくなるので、ゆっくりしたスピードで、常に下部腰部の緊張が抜けないよう保ったまま動かすようにコントロールします。
以上のことを繰り返し、慣らしながら徐々にしゃがみ込む範囲を下げていきます。
2-4、ベンチ・スクワット
スクワットのボトム・ポジションの時にベンチに座れるように補助をつけるやり方です。スクワットをする時に、ベンチを跨いで行うか、もしくは少しベンチにお尻が乗るようにベンチの端に位置します。
スクワットのフォーム自体はノーマルと同じです。ベンチにも完全にペタンと座り込まないようにします。座り込むと、腰部の緊張が抜け、とても危険な状態になります。
腰を降ろす時もゆっくり行い、ベンチにはお尻が少し触れたらそれを合図に立ち上がるようにします。ベンチにより重さを補助するのでなく、感覚を入力することで筋出力を上げ、発揮タイミングを掴むような感じで行います。
3、周りに影響されない
ジムに通っていると、大抵、フリー・ウェイトをやっている人たちの顔ぶれは決まってきているので、それとはなしに顔見知りになっていきます。そこでウェイトを担いでいると、つい見栄で重い重量を挙げたくなってしまいます。
それも分かる気はしますが、周りに流されず目的をもってワークアウトを行ってください。少しでもフォームが崩れるようなら負荷が強すぎる可能性があります。
4、ウェイトの位置を変えるとどうなるか
4-1,フロント・スクワット
よく、フロント・スクワットはバックス・スクワットに比べて上体が立つので腰部での負担が少ない、という話を聞くことがあります。先ずフォーム的にNSCAでは何故かフロント・スクワットもバック・スクワットと同じような下半身のポジショニングで行わせようとしますが、解剖学的に無理です。重量が軽ければできますが、重量が上がってくるにつれ、下肢のポジショニングをバック・スクワットと同じにしていると、上体を立てるにつれ、後にひっくり反ってしまいます。それを防ぐために上体を前傾させるのですが、フロントスクワットだと肩の前でウェイトを保持するので、上体を前傾させるとウェイトを前に落としてしまいます。
それを防ぐためには膝を前方に移動し、ウェイトの垂直線上の過重ラインを土踏まず上に戻してやる必要があります。すると踵が浮いてくるので、踵の下に噛ませものをして足裏全体に過重が乗るようにし、安定化を図り、膝の負担を軽減します。
股関節と脊柱の伸展(そらし)が柔らかい人は、そのような修正をかけなくてもできますが、硬い人や痛みがある人には難しいと感じます。
また、腰痛の出方の種類にもよると思いますが、フロントスクワットが特に腰痛にたいし勝っている種目とも思えません。
4-2,ジェファーソン・スクワット&ハック・スクワット
ウェイトを上体に担ぐから腰に負担がくるのでは?ということでウェイトを下にしてしまえば良いかも、と種目を考えてみたところジェファーソン・スクワットやハック・スクワットがありました。
実際、行ってみた感覚から言って、デッド・リフトをやってるのに感じがにてます。よく考えたら、デッド・リフトのシャフトの位置が違ってるだけのようなモノではないか。デットが下部腰部から臀部、ハムストリングまでを重点的に鍛える種目であるのに対し、ハックスクワットはシャフトを足の後ろ側で把持し持ち上げる動作で、四頭筋などに重点的に働くようです。
ジェファーソンはシャフトを跨いで立ち、体の前後でシャフトをオルタネティッド・グリップで持ち、スクワットします。体が捻れるので、それを嫌う場合はなるべく足をシャフトに平行に位置させるのでなく、半身に開くように位置します。
右足と左足で効果が違ってきますが、ウェイトの重心がちょうど体の重心の真下に来るので、これが一番腰には負担が少ないような気もします。
ただし、重量がましてくると、デットと同じで背中が丸まってくるので、まず上体をキープできる筋力が元々ないとあまり効果的ではないかも。
ハックスクワットのやり方はこちらをご覧ください。
一般的なやり方
上体を立てたやり方
5,まとめ
今回は、具体的な方法の検討をいろいろしてみました。
これが必ず正しいというわけではないので、皆様もご自身の状態にあったやり方をいろいろ試してみて見つけてもらうとよいと思います。
その際、くれぐれもウェイトは軽めから、ということで。あと、自己責任で。
この記事が皆様の何かにお役に立てることを期待してます。では、この辺で。
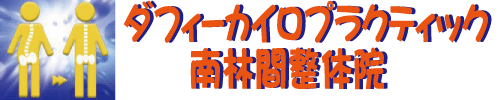





“腰痛からバーベルスクワットへの復帰と予防について” に対して1件のコメントがあります。
この投稿はコメントできません。