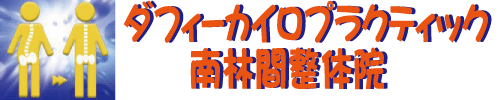健康に関する人工甘味料の影響について
人の事、言えないな~。
健康に関わる仕事をしているくせに、高脂血症(脂質異常症)になってしまいました(涙)
常連のクライアント様だったらご存じのように、私は極度の甘党なので、徳用のチョコレート袋なら2日で1袋を1人で平らげてしまいます。そんな生活を続けていたら、ついにLDLコレステロールが169になってしまいました!
ついでに総コレステロールと中性脂肪も血糖値も異常値です。
そこで、食事療法に取り組むことになりました。
と言っても、間食とソフトドリンク類を摂るのを止めただけですけどもね。それだけでも1ヶ月半で6㎏以上体重が落ちました(元の体重の10%以上)。
しかし、甘いものが食べたい。
ってことで、低カロリー甘味料ってどうなんだろうと思い、今回、深堀りしてみました。
今回の記事では、
①ダイエット目的の砂糖代替品の甘味料全般の紹介。
②砂糖代替品の従来言われていたメリット・デメリット
③最近の研究から言われてきた砂糖代替甘味料の危険性
④総括として、個人的にダイエット目的に使用おすすめ甘味料とは?
という内容で情報をお伝えしたいと思います。
甘味料の種類
| 炭水化物or非炭水化物 | 分類 | 品名 | ||
| 糖質系甘味料
(炭水化物) |
砂糖 | 白砂糖(スクロース/ショ糖)、グラニュー糖、黒砂糖(含蜜糖)、など | ||
| でんぷん由来の糖 | ブドウ糖、胚芽等、果糖、水飴、異性化糖、マルトースなど | |||
| その他の糖 | フラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、キシロオリゴ糖、乳化オリゴ糖、乳糖、蜂蜜、など | |||
| 糖アルコール | ソルビトール、マンニトール、マルチトール、還元水飴、キシリトール、など | |||
| 非糖質系甘味料
(非炭水化物) |
天然甘味料 | ステビア、甘草(グリチルチリン)、羅漢果 | ||
| 人工甘味料 | サッカリン、アステルパーム、アステルファムK、スクラロース | |||
甘味料の説明では必ずと言っていいほど出てくる、上記の表。この回でも、やっぱりこれは外せないので載せておきます。
砂糖について
甘味料とは、食品に甘みを加える調味料のことで、代表的なものは「砂糖」です。砂糖はサトウキビやてん菜から抽出されたショ糖(スクロース)が主成分です。ショ糖はブドウ糖(グルコース)と果糖(フルクトース)が結合したものです。
因みに砂糖のカロリーは、白砂糖(上白糖)で100gあたり391Kcalです。1gあたり3.9Kcalなので、炭水化物1gあたり4Kcalとほぼいっしょです。大さじ1杯(約9g)で約35Kcal、小さじ1杯(約3g)で約12kcalとなるのも覚えておくと便利な数値です。
一部で「砂糖は水分を吸収しやすく、酵母や細菌の栄養源になるため、食品が腐りやすくなる」という文言を見かけることがありますが、一般的には砂糖は防腐効果が高い食材とされています。
食材には炭水化物やたんぱく質と結合している水分の他に、自由水という水分が含まれていて、これが細菌や微生物の繁殖に使われます。砂糖は保水性があるので、自由水と結合することで細菌繁殖に使われることを防いでくれます。食品中の砂糖濃度が65%以上になると、大部分の微生物の増殖が抑えられると言われています。ジャムや羊かんなどが保存性が高いのはそのためです。
その他に、砂糖は食材を柔らかくする、照りやツヤを付けるなどの作用もあり、料理に広く使われています。
砂糖を摂取した時の消化のメカニズム
甘みは、味を感じ取る味蕾という器官で察知します。味蕾は舌の先端や側面、奥の部分で多く存在しているほか、軟口蓋(上あごの奥)や喉の奥にも存在しています。味蕾で察知した味の情報はそれぞれの部位に対応した神経を通して脳に伝えられます。舌の前2/3は顔面神経(鼓索神経)、舌の奥1/3は舌咽神経、軟口蓋や喉頭(のどの方)は迷走神経が支配しています。
通常、食事すると炭水化物は小腸で、プドウ糖(グルコース)に分解され、吸収されます。砂糖の場合は、ショ糖(スクロース→ブドウ糖と果糖が結合したもの)とブドウ糖に分解されます。血中に入ったグルコースが膵臓に入ると、インスリンが分泌されて、血中のブドウ糖は筋肉や脂肪に取り込まれ、血糖値の濃度を元に戻します。過食や、インスリンの分泌がもともと少ない人(インスリン分泌障害)、インスリンの働きがもともと悪い人(インスリン抵抗性)、などはインスリンの効きをよくするため過剰に分泌しようとし、膵臓が働きすぎます。この状態が慢性的に続くと、膵臓が疲労してしまい、インスリンの分泌機能が低下します。これが糖尿病と呼ばれる状態です。
人工甘味料の種類
一般的に使われる砂糖以外の甘味料としては、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会資料「令和元年度 マーケットバスケット方式による 甘味料の摂取量調査の結果について・令和2年 10 月 14 日資料5」を参考にしますと、評価されていた甘味料としては①~⑧が挙げられていました。それに加えて一般的に使われている甘味料として⑨~⑩などがあります。
①アステルパーム
②アセスルファムカリウム(K)
③アドバンテーム
④グリチルリチン酸(甘草抽出物)
⑤サッカリン
⑥スクラロース
⑦ステビア
⑧ネオテーム
⑨キシリトール
⑩D-ソルビトール
今回は、カロリー制限のための甘味料を調べるという目的なので、低カロリー甘味料に的を絞って説明します。
微糖系飲料や0キロカロリーの清涼飲料水の多くで使われているのが、
・アセスルファムカリウム(ほとんどがアセスルファムKと明記しています)
・スクラロース
お菓子などの固形物などに使われることが多いのが、
・ソルビトール
・キシリトール
・エリスリトール
・ステビア
・アステルパーム
などです。
糖質系甘味料では、オリゴ糖や糖アルコール類(ソルビトール、キシリトールなど)が消化・吸収されにくいため低カロリー食材として使用されます。非糖質系甘味料では、砂糖に比べて非常に高い甘みを持つため、砂糖に比べて極端に使用量が減り、そのため摂取カロリーが非常に低カロリーとなるためダイエット食材として使用されます。
従来言われていた人工甘味料のメリット
人工甘味料にはブドウ糖が含まれないないので、一般的には摂取しても血糖値が上昇しないと言われています。したがってインスリンも分泌されず、脂肪に取り込まれるブドウ糖もないので太らないとされています。
特に糖尿病患者の食事療法において、血糖値やインスリン分泌の影響を与えないので有用とされていました。
従来言われていた人工甘味料のデメリットと一日摂取上限値
日本人の人工甘味料の摂取量
消費者庁のホームページに「マーケットバスケット方式による年齢層別食品添加物の一日摂取量の調査」という項目があります。そこに人工甘味料のみをターゲットにした成人日本人の一日の摂取量を調べたものが再審で令和元年版があります。甘味料を含めた食品添加物全般のものが最新版として令和5年度のものがあります。
令和元年で「アセスルファムカリウムが1.779 mg/人/日、スクラロースが 0.752 mg/人/日、ステビア抽出物が0.579mg/人/日、グリチルリチン酸(甘草抽出物)が0.401mg/人/日、サッカリンが0.144mg/人/日、アスパルテームが0.055mg/人/日、アドバンテーム及びネオテームは 0 mg/人/日」
令和5年で「アセスルファムカリウムが 1.6 mg/人/日、スクラロースが 0.99 mg/人/日、ステビア抽出物が 0.52 mg/人/日」。
FDA(米国食品医薬品局)とWHOが定める人工甘味料のADI(許容一日摂取量/人が生涯にわたって毎日摂取しても、健康に悪影響がないと推定される量)。それと調査によって割り出された日本人の一日推定摂取量と、ADIに対する割合を表にしました(消費者庁「令和元年度 WHO の非糖質甘味料の使用に関するガイドラインと国内における非糖質甘味料の摂取量推計について」より作成)。
| FDA基準
(体重1kgあたり/一日) |
WHO | 日本人の推定 一日摂取量 (mg/人/日) |
体重58.8㎏の成人の一日許容量(mg/人/日) | 日本人推定摂取量の対ADI比(%) | |
| アスパルテーム | 40mg | 40 | 0.05 | 2352 | 0.002 |
| アセスルファムカリウム | 9mg | 15 | 1.78 | 882 | 0.20 |
| アドバンテーム | 5mg | 5 | 0 | 294 | 0 |
| グリチルリン酸 | – | – | 0.40 | – | – |
| サッカリン | 5mg | 3.8 | 0.14 | 223 | 0.06 |
| スクラロース | 5mg | 15 | 0.752 | 882 | 0.09 |
| ステビア抽出物 | – | 4 | 0.579 | 235 | 0.25 |
| ネオテーム | 0.3mg | 1.0 | 0.0002 | 59 | 0.0003 |
アスパルテームは、特定の条件下でフェニルアラニンという物質に分解されるため、フェニルケトン尿症の人は摂取を制限する必要がある。
人工甘味料は消化吸収されず、腸内の水分を引き上げるため、腸内の浸透圧を高める働きがあり、腸管からの水分吸収を阻害するため、下痢を引き起こす可能性があるとされており、従来の基準は、その観点で摂取許容量を設定されているようです。
ただ、アスパルテームの許容一日摂取量は、アスパルテームが200~300ミリグラム入っているダイエット清涼飲料水500ミリリットルボトルであれば、1日に8~12本に該当します。日本人の推定摂取量は令和4年度でも6.58ミリグラムと推計され、ADIの許容一日摂取量のわずか0.3%程度であることが報告されています。
最近の研究から新たに言われだした人工甘味料の危険性
SNS上で低カロリー食事、低カロリーおやつ等で作る動画や情報見ると、必ずと言っていいほど砂糖の代替品として使われるのが羅漢果ですが、羅漢果を謳っている商品の中には、ほとんどの主要成分がエリスリトール(90%以上など)で、羅漢果エキスは少量しか含まれていないケースも見られますので注意が必要です。
つまり天然甘味料を謳っていても、実は中身はほとんど人工甘味料だったということも少ないということです。その点は注意が必要です。
そして、その人工甘味料に健康被害をもたらす作用があるといった情報が、近年やたらと増えてきました。そこでこれからは、それらの情報をご紹介していきます。
その中で頻繁に出てくる専門用語で「コホート」というのがあります。一般には馴染みのない用語なので、これだけ説明を加えておきます。内容はAIから。
「コホートとは、[共通の特徴を持つ集団]のことです。、疫学研究におけるコホート研究では、特定の要因にさらされた集団(コホート)を長期間追跡し、その後の健康状態の変化を観察することで、病気の原因を特定しようとします。」
人工甘味料の危険性に関する最近の研究の一覧
色んな情報が出ていますので、一旦、近年中に発表された人工甘味料のリスクに関する研究報告を一覧にして、整理してみました。まずは用語の説明から。
アステルパームとアスパルテームについて
名前が似すぎてこんがらがってしまいます(怒)!
どちらも人工甘味料ですが、化学構造と甘味質が異なります。アスパルテームはアミノ酸から構成され、アステルパームはスルホンアミド系の化合物です。また、アスパルテームは砂糖の約200倍の甘さ、アステルパームは砂糖の約200~250倍の甘さを持つとされています。
アスパルテーム (Aspartame)は、アスパラギン酸とフェニルアラニンという2種類のアミノ酸が結合した化合物です。砂糖に近い自然な甘味質を持ち、苦味をマスキングする効果や風味を増強する効果もあり、ダイエット飲料、ガム、ヨーグルト、医薬品など、幅広い食品に使われています。
アスパルテームについて
【アスパルテームと人間の健康:発がん性および全身的影響に関するミニレビュー】
| 【Aspartame and Human Health: A Mini-Review of Carcinogenic and Systemic Effects】
出典;J. Xenobiot. 2025 Jul 7;15(4):114. doi: 10.3390/jox15040114 《概要》 アスパルテームは体内に摂取されると、主にアスパラギン酸、フェニルアラニン、メタノールに分解され、さらに生理活性化合物へと変換され、人体への様々な健康影響をもたらす。アスパルテームの長期摂取が、がんを含む様々な健康状態のリスク増加と関連している可能性があることが示唆されているが、他方、癌との関連性が見られない、もしくは癌を抑制する結果を見る研究も存在する。 2018年から2024年の間に英語で発表された最近の研究に重点を置き、幅広い期間にわたる査読済み研究の文献レビューを実施した。 ・いくつかのランダム化研究では、砂糖をアスパルテームのような非栄養性甘味料に置き換えることで、適度な減量とカロリー摂取量の減少が期待できることが示されてる。一方で、このような甘味料は逆説的に食欲を増進させたり、代謝異常を引き起こしたりする可能性があると主張する研究もる。いくつかの観察研究および実験研究では、アスパルテームの摂取と代謝、心血管、および胃腸への影響との関連が示されている。 ・アスパルテームは食後血糖値とインスリン値への影響が無視できるほど小さいことがよく挙げられ、糖尿病患者の食事療法によく用いられている。しかし、10万人以上のフランス人成人を対象としたコホート研究において、特に摂取量が通常の食事摂取量を超えた場合、アスパルテームの大量摂取と心血管イベントのリスク増加との間に有意な関連性があることを報告(下に載せている論文)されている。 ・観察データは、アスパルテームを含む人工甘味料とインスリン抵抗性および非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)のリスク上昇との関連を示唆しており、腸内細菌叢の変化やインクレチンシグナル伝達の阻害が原因となっている可能性がある。 ・米国食品医薬品局(FDA)や欧州食品安全機関(EFSA)などの規制当局は、アスパルテームは、摂取量が定められた一日摂取許容量(ADI)(米国では50 mg/kg体重/日、EUでは40 mg/kg体重/日)の範囲内であれば、人体への摂取は安全であると主張している。FDAによると、体重70 kgの成人がADIを超えるには、毎日10~14缶以上のダイエットソーダを摂取する必要があるとのこと。 ・国際がん研究機関(IARC)などの組織による新たな精査を促し、最近、アスパルテームを「ヒトに対して発がん性の可能性がある」(グループ2B)に分類した。 ・結論として、in vitroおよびin vivo研究の両方において、アスパルテームの遺伝毒性および発がん性について検討が行われてきたが、依然として結論は出ていない。一部の研究では潜在的なリスクが示唆されているが、疫学的証拠はアスパルテームの摂取とがんリスクとの明確な関連性を確立していない。現在の科学文献に基づくと、アスパルテームを遺伝毒性または発がん性があると明確に分類することはできない。 |
【食品甘味料としてのアスパルテームの安全性と関連する健康被害】
| 【Aspartame Safety as a Food Sweetener and Related Health Hazards】
出典;Nutrients .2023 Aug 18;15(16):3627. doi: 10.3390/nu15163627 《概要》 FDAおよびその他の規制当局はアスパルテーム摂取の1日許容摂取量のガイドラインを設定しているが、今日その安全性については多くの疑問がある。 摂取後、アスパルテームは腸管でアスパラギン酸、フェニルアラニン、メタノールという 3 つの成分に分解される。これらの成分は、果物や野菜などの他の食品にも天然に含まれており、アスパルテームを含む食品では、他の食物源由来のものと同じように体内で処理される。 毎日のアスパルテーム摂取によるメタノール摂取量の上位90%は、FDAが設定したメタノール摂取の最大安全レベル7.1〜8.4 mg / kg /日の25分の1であり、ペクチン、果物、野菜、アルコール飲料などの他の天然源によるメタノール摂取量よりもはるかに低い。 毒物学の基本的な教義は、すべての物質はある濃度では有害であるということ。 様々な動物種の実験データによると、アスパルテームを長期摂取すると、腎組織におけるフリーラジカル産生が用量依存的に増加し、腎障害も引き起こされることが示されている。 アスパルテームとその代謝物が神経系に及ぼすこれらの多様な生化学的影響は、分解によって遊離するフェニルアラニンとアスパラギン酸という 2 つのアミノ酸によるものである可能性が高い。アスパルテーム34mg/kg/日を2週間摂取した小児を対象とした臨床研究では、プラセボ群と比較して血漿中のフェニルアラニンとチロシンのレベルが上昇したことが証明された。フェニルアラニン濃度の上昇は、カテコールアミン、セロトニン、ドーパミンのレベル低下と関連していて、神経毒性を有し、モノアミン神経伝達物質の産生に影響を及ぼす。 アスパルテームとその代謝物が神経系に及ぼすこれらの多様な生化学的影響は、アスパルテームを摂取した動物と対照群とを比較した様々な生体内研究で記録された。空間見当識が変化し、迷路試験での脱出潜時が長くなる。また、不安の増加も見られた。 アスパルテームを30 mg/kg/日投与された単極性うつ病患者にうつ病、不眠症、記憶障害、易刺激性、およびよく見られる片頭痛やその他のタイプの頭痛が見られた。 一部の臨床研究や動物実験では、ADI (最大許容1日摂取量/40~50mg/kg体重/日)を下回るまたは ADI でアスパルテームを毎日摂取すると神経行動学的影響が生じることが示唆されているが、欧州食品安全機関 の専門家は、詳細かつ系統的な分析を行った結果、アスパルテームおよびその分解物は、現在の暴露レベルではヒトの摂取に安全であると結論付けた。 |
動物実験で健康被害が出たというレベルでも、人間に投与するとほとんどが反応を示さない、というのがほとんどでした。ただ、長期的にみると健康被害が起こりそうだということです。現在、確認されているのは心血管障害と、癌リスクの増加です。日本では認知機能も悪化すると騒いでいる医療系インフルエンサーやマスコミもいますが、動物実験のみで、人間での関連は不明です。
エリスリトールについて
エリスリトールの研究論文を読むにあたり、「内因性エリスリトール」と「外因性エリスリトール」というワードが散見されます。そのことについて軽く触れておきます。
体内のエリスリトールには体の中で生成されもの(内因性)と、食べ物から摂取されたもの(外因性)の2種類があります。前者は体内グルコースからペントースリン酸経路(PPP)を介して合成されたものです。また、PPPを介して血中エリスリトールの5~10%はエリスロン酸に代謝され、残りは尿として排出されます。
下記の論文4編で述べられていることは、エリスリトールが心血管疾患と関連するというものもあれば、関連無いというものもあり、まちまちであるという事でした。
【ARIC研究における高齢者のエリスリトール、エリスロン酸、および心血管疾患のアウトカム】
| 【Erythritol, Erythronate, and Cardiovascular Outcomes in Older Adults in the ARIC Study】
出典;JACC Add.2025 Mar;4(3):101605. doi: 10.1016/j.jacadv.2025.10160 《概要》 1987年から1989年に採取された第1回目ARIC(米国の4つの地域から参加した成人におけるCVD(動脈硬化性心血管疾患)発症率に関する前向き観察研究)のサンプルのメタボローム解析により、エリスリトールと冠動脈性心疾患( CHD) との関連が示された。5回目ARIC の診察( 2011~2013年) におけるエリスリトールおよびエリスロン酸と将来の心血管疾患アウトカムとの関連性を調査した。 エリスリトールは摂取後、消化管で急速に吸収され、60~90分で血中濃度がピークに達し、摂取後24時間以内に60~85%が尿中に排泄され、48時間後には約90%が尿中に排泄される。エリスリトールの摂取は、血糖値やインスリン値に影響を与えない。血中エリスリトールの約10%が、ペントースリン酸経路(PPP)を介してエリスロン酸に代謝される。体内のグリコーゲンからPPPを介して内因的にもエリスリトールは生成される。 ブドウ糖摂取により体内でエリスリトールの生成が誘発され、体重増加および高血糖と関連してる。そのため、血糖ストレスが大きい人はエリスリトールの内因性生成が増加している可能性があり、これは単に血糖異常のマーカーである可能性がある。 人工甘味料の摂取は、大規模な前向き研究(平均年齢 42.22 歳、追跡期間の中央値 9 年)において、冠状動脈疾患および脳卒中の増加に関連することが示された。しかし、人工甘味料の摂取量が多い人は、食生活も悪く(果物、野菜、食物繊維が少なく、加工肉、乳製品、ナトリウムが多い)、身体活動が少なく、喫煙する傾向が高く、BMI も高かった。これらはすべて、冠状動脈疾患および脳卒中の危険因子である。 エリスリトールは、PPPで内因的に産生され、冠動脈性心疾患(CHD)および心血管疾患(CVD)との関連が指摘されてる。本研究では、血中エリスリトールおよびその代謝物であるエリスロン酸の濃度上昇は、BMIの上昇、高血圧、糖尿病、脂質低下薬の使用、および心血管バイオマーカー(N末端プロB型ナトリウム利尿ペプチドおよびトロポニン)の上昇と関連していた。血中エリスリトールおよびエリスロン酸は、心不全(HF)の発生率、全死亡率および心血管疾患による死亡率と関連していた。エリスロン酸は、冠動脈性心疾患(CHD)および脳卒中の発生率とも関連してた。 |
【エリスリトールの摂取は、健康な被験者において、グルコースではなく血小板反応性と血栓形成能を高める】
| 【Ingestion of the Non-Nutritive Sweetener Erythritol, but Not Glucose, Enhances Platelet Reactivity and Thrombosis Potential in Healthy Volunteers-Brief Report】
出典;Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. 2024 Sep;44(9):2136-2141. 《概要》 一晩絶食した健康な被検者10名(30.1±11歳、男性40%)に水に混ぜたブドウ糖30gを摂取、10名(30.5±8歳、男性50%)にエリスリトール30gを摂取させ、摂取前と摂取30分後に採血した。エリスリトール摂取量は一般的な食品によく含まれる量であり、2013~2014年の国民健康栄養調査データおよび食品医薬品局(FDA)提出書類に基づく被験者の1日摂取量に基づいている。
エリスリトール摂取後は、血中エリスリトール濃度がベースライン値の1000倍以上(P <0.0001)となったが、ブドウ糖摂取後は、血中エリスリトール値は変化なし、血中ブドウ糖濃度は若干上昇を見せた(P =0.002)。エリスリトール摂取後は血小板凝集反応の顕著な増加が観察された。ブドウ糖摂取は血小板凝集に影響を与えなかった。
エリスリトールは、血小板濃厚顆粒マーカーであるセロトニン(TRAP6 [トロンビン活性化ペプチド6] についてはP <0.0001、ADPについてはP =0.004)および血小板α顆粒マーカーであるCXCL4(CXCモチーフリガンド4、 TRAP6についてはP <0.0001、 ADPについてはP =0.06)の刺激依存性放出を増強することによって、直接的な血栓形成促進効果を引き起こす可能性がある。
今後の課題は、①研究規模が小さいため、さらに他のコホートの研究結果が必要である。②エリスリトールは急速に吸収され、摂取15分後に血中濃度が上昇し、血小板反応が現れるが、血小板寿命は5~7日であるので、さらなる長期の研究が必要。
|
いままでの砂糖代替品の研究は、血糖値コントロールと体重減少に焦点が当てられているが、近年、循環器疾患との関連が取りざたされています。植物性ポリフェノールが血小板阻害に役立つとの言及が論文内にもありますので、食事で積極的に摂っていきたいものです。
【血清エリスリトールと男性コホートにおける全死亡率および原因別死亡率のリスク】
| 【Serum Erythritol and Risk of Overall and Cause-Specific Mortality in a Cohort of Men】
出典;Nutrients.2024 Sep 14;16(18):3099 doi: 10.3390/nu16183099 《概要》 血清エリスリトールの生化学的状態と全死亡率および死因別死亡率との関連性を調査するため、以前のがん予防の研究(50~69歳のフィンランド人男性喫煙者対象;1985~1993年)の参加者を対象に前向きコホート解析を実施した。解析には4468人(癌症例2606名、非症例1862名)が含まれ、平均19.1年の追跡期間中に3377人が死亡した。 血中エリスリトールは全死亡リスクの上昇と関連していた(HR = 1.50 [95% CI = 1.17–1.92])。血中エリスリトールと心血管疾患死亡リスクの間には正の相関が認められ(HR = 1.86 [95% CI = 1.18–2.94])、この相関は心疾患死亡リスクの方が脳卒中死亡リスクよりも強かった(それぞれHR = 3.03 [95% CI = 1.00–9.17]、HR = 2.06 [95% CI = 0.72–5.90])。癌死亡リスクもエリスリトールと正の相関を示した(HR = 1.54 [95% CI = 1.09–2.19])。血中エリスリトールと全死亡リスクの関連は、55歳以上の男性および拡張期血圧88mmHg以上の男性でより強かった(交互作用のp値はそれぞれ0.045および0.01)。本研究は、血中エリスリトール値の上昇が、全死亡リスク、心血管疾患リスク、および癌リスクの上昇と関連していることを示唆している。 エリスリトールは血小板を活性し、血栓の生成を促進する。その反応は摂取後2日間続く。 |
【エリスリトールは心血管代謝疾患の潜在的原因となる:メンデルランダム化試験】
| 【Erythritol as a Potential Causal Contributor to Cardiometabolic Disease: A Mendelian Randomization Study】
出典;Diabetes. 2024 Feb 1;73(2):325-331.doi: 10.2337/db23-0330 《概要》 外因性エリスリトールは血漿グルコースまたはインスリンを増加さず、グルカゴン様ペプチド1およびコレシストキニンの分泌を増加させ、胃内容排出を減少させる。2型糖尿病(T2D)の人では、エリスリトールを毎日補給すると、4週間にわたって内皮機能が急激に改善し、大動脈硬化が減少すると報告されている。しかし、エリスリトールの摂取量増加は、観察研究において心臓代謝への有害な影響と関連付けられている。 具体的には、エリスリトール1μmol増加ごとに主要な心血管イベントのリスクが16~31%増加するという報告がある。試験管内および生体外での研究では、エリスリトールはベースラインの空腹時濃度の4~10倍の濃度で血小板凝集を促進することが示されている。これらのデータを総合すると、エリスリトールの増加(内因性産生&外因性摂取)は、急性/短期摂取後には有益な代謝/内分泌作用が期待されるものの、心臓代謝に悪影響を及ぼす可能性があることが示唆されている。 観察データは、交絡因子や逆因果関係によってバイアスを受ける可能性がある。2型糖尿病と血糖異常は心血管リスク因子であり、内因性エリスリトール産生を増加させる可能性がある。心血管リスク因子である慢性腎臓病(CKD)は、内因性および外因性エリスリトールの排泄に影響を与える可能性がある 。加齢およびトリグリセリド値の上昇はエリスリトールの増加と関連している。心血管代謝疾患(CMD)リスクのある人は外因性エリスリトールの摂取量が多い可能性がる。 2標本メンデルランダム化(MR)は交絡を起こしにくい傾向があるので、エリスリトール、T2D、および関連する CMD の間の潜在的な因果関係と影響の方向を調べるために双方向 MR を実施した。 公開されている最大規模のGWASの要約統計値を用いて、NIHR(国立衛生研究所)、METSIM(男性メタボリックシンドローム)、Twins UK、KORA(アウクスブルク地域共同健康研究/アウクスブルク地域共同健康研究)を含むヨーロッパ系コホートにおいて単変量MR解析を実施。 MR分析結果は、エリスリトールの増加がBMIを低下させ、その結果としてBMI調整ウェスト・ヒップ比(WHR)を増加させる可能性があることを示唆している。しかし、エリスリトールが冠動脈疾患(CAD)、T2D、空腹時血糖、クレアチニンを使用した推定糸球体濾過率(eGFR)、またはCKDを増加させるという証拠は見つからず、また、評価した心臓代謝特性と人体計測特性がエリスリトール濃度に有意な影響を与えるという証拠も見つからなかった。総合的に、エリスリトールとCMDの因果関係の証拠は見つからなかった。 |
アスパルテーム、アセスルファムカリウム、スクラロースについて
この3種類は日本でも頻繁にお目にかかります。特にアセスルファムカリウムとスクラロースの組み合わせは多いと思います。食品の成分表での表記は「アセスルファムK」です。
【妊娠中の人工甘味料摂取と妊娠糖尿病発症率の相関分析】
| 【Correlation Analyses of the Consumption of Artificial Sweeteners During Pregnancy and the Incidence of Gestational Diabetes Mellitus】
出典;Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity.2025 May 8;18:1527–1538.doi: 10.2147/DMSO.S513544 《概要》 中国では現在、最も一般的な3種類の人工甘味料(スクラロース、アスパルテーム、サッカリン)の使用が許可されている。妊娠糖尿病(GDM)と人工甘味料との関連を調査。 広東省の病院に入院中の妊婦422名を対象に、便宜的サンプリングによる調査を実施した。質問票では、一般情報、人工甘味料の摂取状況、その他のGDM関連因子について収集した。国際糖尿病妊娠研究グループ協会(IADPSG)によると、GDMは妊娠中のいずれの時期においても、75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)の基準を満たした場合に診断される。人工甘味料の摂取状況は、4段階評価尺度に基づき、低摂取群と高摂取群に分類した。 平均年齢は32±3.73歳、GDM(妊娠糖尿病)発症率は13.74%。人工甘味料の摂取量が多い群(56.90%)のGDM発症率は、摂取量が少ない群(43.10%)よりも高かった(p < 0.05 )。人工甘味料の摂取量の増加は、GDMリスクの上昇と関連していた(オッズ比2.66、95%信頼区間1.48-1.78 )。BMI層別解析において、人工甘味料の摂取量が多いことはGDMリスク因子だった。 |
【人工甘味料と心血管疾患リスク:前向きNutriNet-Santéコホート研究の結果】
| 【Artificial sweeteners and risk of cardiovascular diseases: results from the prospective NutriNet-Santé cohort】
《概要》 NutriNet-Santéコホートに参加した103,388名(平均年齢42.2±14.4歳、女性79.8%、904,206人年) のデータを使用し、最初の2年間の追跡期間中の24時間食事記録の平均数は5.6件(標準偏差3.1)であった。 人工甘味料の消費量で、非消費(6万5,028[62.90%])、低消費(1万9,221人[18.59])、高消費量(1万9,139人[18.51%])の3つの群に分けられた。低消費量と高消費量は、男女別の中央値( 男性16.44mg/日、女性18.46mg/日)を基準に分類された。 コホート全体のうち、0.94%(n=1,639)の参加者が参加(本集団研究では981人) 以降に死亡し、9.4%(n=16,306)が今後アンケート調査を受けたくないという理由で脱落した。参加者の37.1%が人工甘味料を摂取していて、人工甘味料の平均摂取量は、全参加者で15.76 mg/日、消費者のみで42.46 mg/日であり、これは卓上甘味料約1袋またはダイエットソーダ100 mLに相当する。人工甘味料を消費した参加者のうち、低摂取者カテゴリと高摂取者カテゴリの平均摂取量はそれぞれ7.46 mg/日と77.62 mg/日であった。非消費者と比較して、高摂取者(未調整比較)は若年で、BMIが高く、喫煙率が高く、身体活動が少なく、減量ダイエットをしている傾向があり、総エネルギー摂取量が低く、アルコール、脂質(飽和および多価不飽和)、食物繊維、炭水化物、果物および野菜の摂取量が低く、ナトリウム、赤身肉および加工肉、乳製品、砂糖無添加飲料の摂取量が高かった。 分析結果では、人工甘味料の総摂取量の増加と心血管疾患のリスク上昇は関連していた(イベント数1,502件、ハザード比[HR]:1.09、95%信頼区間[CI]:1.01~1.18、p=0.03)。摂取量が多い(性別別の中央値を超える)人の絶対発生率は10万人年あたり346人、摂取しない人では314人であった。 人工甘味料は特に脳血管疾患リスクとの関連が強かった(1.18、95%信頼区間1.06~1.31、P=0.002)。脳血管疾患の罹患率は、10万人年当たり高消費量群が195件、非消費群は150件だった。 アスパルテームの摂取が脳血管疾患リスクの増加と関連し(HR:1.17、95%CI:1.03~1.33、p=0.02)、罹患率は10万人年当たり高消費量群が186件、非消費群は151件であった。 アセスルファムカリウム(HR:1.40、95%CI:1.06~1.84、p=0.02)とスクラロース(1.31、1.00~1.71、p=0.05)は冠動脈性心疾患(イベント数730件)のリスク増加と関連していた。アセスルファムカリウムの罹患率は10万人年当たり高消費量群が167件、非消費群は164件で、スクラロースはそれぞれ271件および161件だった。 脳血管疾患または冠動脈疾患の種類ごとに、スクラロースと血管形成術のリスク(n=477; 1.60, 1.17~2.21, P=0.004)および人工甘味料総量と一過性虚血イベント(n=598; 1.18, 1.05~1.33, P=0.006)との間に直接的な関連が認められた。 BMI変数別の人工甘味料は、心血管疾患全般、冠動脈疾患、脳血管疾患において統計的に有意差はなかった(いずれもP>0.05)。 総じて、人工甘味料を砂糖の代わりに使用しても、心血管疾患(CVD)の結果には何のメリットもないことを示している。 |
フランスにはフランス保健省から助成を受けたNutriNet-Santé研究というのが2009年から始まっていて、そのデータを使って分析された人工甘味料についての一連の研究があります。その一つが、この人工甘味料と心血管リスの関係について分析したものです。その他、下記には人工甘味料と癌との関連について分析したもの、砂糖も含めて分析したものをご紹介しています。
【人工甘味料とがんリスク:NutriNet-Santéの人口ベースコホート研究の結果】
| 【Artificial sweeteners and cancer risk: Results from the NutriNet-Santé population-based cohort study】
出典;PLoS Med. 2022 Mar 24;19(3):e1003950.doi: 10.1371/journal.pmed.1003950 《概要》 フランスの人口ベースコホートNutriNet-Santé研究(2009~2021年)の成人102,865名が対象となった(追跡期間中央値7.8年)。 人工甘味料の総摂取量が多い人は、非摂取者と比較して全体的ながんリスクが高かった(3,358例、ハザード比[HR] = 1.13 [95% CI 1.03~1.25]、P= 0.002)。特にアスパルテーム(HR = 1.15 [95% CI 1.03~1.28]、P= 0.002)とアセスルファムK(HR = 1.13 [95% CI 1.01~1.26]、P= 0.007)は、がんリスクの上昇と関連していた。乳がん(アスパルテームでは 979例、HR = 1.22 [95% CI 1.01~1.48]P = 0.036)および肥満関連がん(人工甘味料全体では2,023例、HR = 1.13 [95% CI 1.00~1.28]、P= 0.036、アスパルテームではHR = 1.15 [95% CI 1.01~1.32]、P= 0.026)でも高いリスクが観察された。 結論として、特にアスパルテームとアセスルファムKは、がんリスクの上昇と関連していると言える。 |
下記でご紹介している【糖分の多い飲料の摂取とがんリスク:NutriNet-Santéの前向きコホート研究の結果】の論文も同時にお読みください。下の論文は2019年発表のもので、こちらの論文は2022年発表のものです。下の論文は2009~2017年のフランスのNutriNet-Santéコホート研究のデータ(成人101,257名対象)から、今回の論文は同じくフランスのNutriNet-Santéコホート研究で2009~2021年の(成人102,865名対象)で、4年分今回の論文の方がデータが増えていますが、そのためか、人工甘味料の癌リスクについての見解が真逆になっています。
砂糖の健康被害に関して
今まで人工甘味料のデメリットばかり強調してきましたが、一方、砂糖についてのデメリットについても情報を挙げておきます。一般的には砂糖と言えば、高カロリーで、過剰に摂取すると脂肪に変換され、肥満や体重超過、高血糖からくる糖尿病、高脂血症からくる循環器疾患・心疾患などの原因と認識されてきました。
その他にも癌との関連もあるということも発表されています。
【糖分の多い飲料の摂取とがんリスク:NutriNet-Santéの前向きコホート研究の結果】
| 【Sugary drink consumption and risk of cancer: results from NutriNet-Santé prospective cohort】
出典;BMJ.2019 Jul 10;366:l24088. doi: 10.1136/bmj.l2408 《概要》 2009~2017年のフランスのNutriNet-Santéコホート研究のデータから、18歳以上(平均年齢42.2歳、標準偏差14.4歳、追跡期間中央値5.1年)の参加者101,257名(男性 21,533 人(21.3%)、女性 79,724 人(78.7%))が対象として、加糖飲料および人工甘味料添加飲料の摂取量と癌リスクとの関連を評価。 加糖飲料の摂取は、全がん(n=2193、100mL/日増加のサブ分布ハザード比1.18、95%信頼区間1.10~1.27、P<0.0001)および乳がん(693、1.22、1.07~1.39、P=0.004)のリスクと有意に関連していた。人工甘味料入り飲料の摂取は、がんのリスクとの関連は認められなかった。特定のサブ解析では、100%果汁ジュースの摂取は全がんのリスクと有意に関連していた(2193、1.12、1.03~1.23、P=0.007)。 生体インピーダンスデータが利用可能な15,637名の参加者において、加糖飲料の内臓脂肪指数との間に関連が認められた(P=0.04)。人工甘味料入り飲料との関連は認められなかった(P=0.07)。 果汁の摂取と甲状腺がんのリスク増加との関連が観察されている。柑橘類および果汁と皮膚の基底細胞がんおよび扁平上皮がんのリスク増加との関連が観察され、100% 果汁には一般的に高レベルの単糖(この研究では中央値 10.3 g/100 mL、通常のソーダよりも高い場合がある)が含まれており、グリセミック指数は丸ごとの果物よりも高い。 肥満関連がんおよび脂肪蓄積関連がんのリスクが、砂糖入り飲料の摂取と関連している。また、砂糖入り飲料の摂取は内臓脂肪の増加と関連しており、内臓脂肪はアディポカイン分泌と細胞シグナル伝達経路の変化を通じて腫瘍形成を促進する可能性があり、体重とは無関係にがんとの関連に役割を果たしている可能性がある。 多くの国では、公衆衛生当局が推奨する飲料は水だけである。人工甘味料入り飲料の摂取はがんのリスクと関連していなかったが、このサンプルでは摂取量が比較的少なかったため、統計的検出力はおそらく限られていた。 |
【砂糖入り飲料、人工甘味料入り飲料、フルーツジュースの摂取と2型糖尿病の発症率:系統的レビュー、メタアナリシス、人口寄与率の推定】
| 【Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable fraction】
出典;BMJ 2015 ; 351 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.h3576 《概要》 2009 ~ 2010 年の米国 (n=4729、糖尿病のない成人 1 億 8,910 万人) および 2008 ~ 2012 年の英国 (n=1932、4,470 万人) の全国調査のデータを使い、体系的レビューとメタ分析を行い、人工甘味料入り飲料、フルーツジュースの摂取と 2 型糖尿病との関連性を調査し、米国と英国における砂糖入り飲料の摂取による 2 型糖尿病の人口寄与率を推定した。 17のコホート(38,253件の症例/10,126,754人年)から事前に指定された情報が抽出された。砂糖入り飲料の摂取量が多いと、2型糖尿病の発症率が高くなるという関連があり、1日1杯あたり18%(95%信頼区間9%~28%、異質性のI 2 =89%)、肥満調整前後で13%(6%~21%、I 2 =79%)増加した。人工甘味料入り飲料では25%(18%~33%、I 2 =70%)、8%(2%~15%、I 2 =64%)、フルーツジュースでは5%(-1%~11%、I 2 =58%)、7%(1%~14%、I 2 =51%)増加した 砂糖入り飲料の習慣的な摂取は、肥満とは無関係に、2型糖尿病の発症率の上昇と関連していた。人工甘味料入り飲料とフルーツジュースも2型糖尿病の発症率との正の関連を示したが、この結果にはバイアスが含まれている可能性が高い。低カロリー摂取は、体重減少を促すことで、肥満または過体重の成人にとって臨床的に有益となる可能性がある。とはいえ因果関係は確立していないものの、人工甘味料入り飲料とフルーツジュースはどちらも、2型糖尿病の予防において砂糖入り飲料の健康的な代替品となる可能性は低い。 |
人工甘味料に糖尿病予防の効果がないという事が発表され、話題となった論文です。
今までの情報をまとめて、現状ベストと思えるダイエット目的で使える甘味料
砂糖を摂っていると血糖値が上がり、糖尿病になったり、中性脂肪過多から高脂血症→動脈硬化→脳梗塞・心臓血管障害という病気の進行がある、また癌リスクもある、ということから血糖値に作用しない人工甘味料へ切り替えようという考えになります。
しかし、人工甘味料を摂っても癌のリスクが上がり、血栓ができやくなり、脳梗塞や心血管疾患になりやすい、と言われます。
ということは、金輪際、甘いものは一切摂るなってことになります。実際、youtubenの動画で医者の配信者がそのようなことを言っているのが多くいます。
「砂糖入り、もしくは人工甘味料入り、もしくはフルーツジュースなどの清涼飲料水(ソフトドリンク・炭酸医療・スポーツドリンクなどなど)全部に言えることだが、健康を気にするなら飲むな、水だけを推奨する」というようなことを言っています。
う~ん、食べる楽しみがないね。
個人的にはこちらの記事に共感を覚えます。
【「人工甘味料は体に悪い」は盛られすぎている…「アスパルテームの発がん性報告」に現役医師が訴えたいこと】PRESIDENT Online 2023/07/15
厳格な食事制限が必要な病気にでもなったなら仕方がないが。
摂取過多なら是正する必要あるが、たまに摂るくらいなら問題ないと考えます。ただ、SNS上で「ダイエット、食べても太らない」などの過剰な謳い文句でレシピを紹介している調理動画配信者を見ていると、過剰にラカントSを使用していたりします。ああいうのを見てると、どうだろうな~と感じてしまいます。
そのような場合は、甘味料は天然甘味料を使用してみると良いでしょう。
天然甘味料とは、ステビア、甘草(グリチルチリン)、羅漢果などを指します。甘草は漢方の原料にも使われ、用法を間違えると副反応も出やすいので、一般家庭の甘味料としては使わていません。一方、ステビアや羅漢果などは、今回のリサーチでもデメリットを指摘した研究が見つかりませんでした(今後は出るかも知れませんが…)。
従って次回は天然甘味料についての情報をお届けしたいと思います。今回まとめて出そうと思いました、思いのほか長文になってしまったので。
今回はこの辺で。